準備品
おもり・・・ベアリングの玉が良いみたいだけれど、(ネットで手に入る)私は簡単に手に入るナットの大きいのを使った。
(いつかベアリングで作りたい)

糸・・・・・・釣り糸が良い、まず吊ったときにねじれない、おもりで伸びない。
難点は高価なこと。
私は安く手に入る、大工さんが墨壺に使う糸を使った。
微調整の解き、糸のねじれが引っかかってプチプチと動いた。
板・・・・・・2枚(角が立った物が良い)
私の用意したのは、檜材、910×12×30の材2本
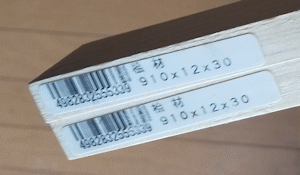
ねじ・・・・ワッシヤーのついた物
「(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ」など
ドリル・・・ねじを埋める穴を最初に開けます。
物差し
ドライバー
振り子の長さの計算
微小振動の単振り子の周期は次のようになります。
T = 2π\(\sqrt{\frac{\large{l}}{\large{g}}}\) 両辺を2乗して
T2 = 4π2\(\large{\frac{l}{9.8}}\) lについてまとめると
l = \(\large{\frac{{g\times{t}^2}}{4\pi^2}}\) となります。
ここでgは重力加速度9.8を入れ、
tに周期を入れれば糸の長さが計算できます。
周期(一階の振れ時間)は、
一番長い糸は60秒に51回振れるように設定します。振れる時間は 51/60です。
2番目の糸は60秒に50回振れるように設定します。振れる時間は 52/60です。
3番目の糸は60秒に52回振れるように設定します。振れる時間は 53/60です。
こういうときは集計表の出番。
小学生からエクセルやオープンオフイスなどの集計表を覚えましょう。
2行目に計算式を見えるようにして入れています。
D列の周期は、B列の総秒/d列の回数です。
E列の長さmは、9.8×周期×周期÷4÷π÷π で計算しています。
F列はE列を100倍してmをcmにて小数点以下2桁表示にしました。
これで準備完了です。
式中のPI() はπ(ぱい)、つまり円周率のことです。
2行目を一つ書いて上から下にコピーすれば計算してくれます。
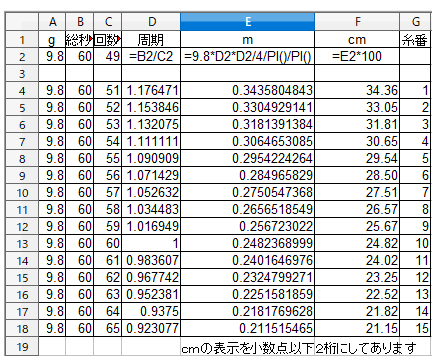
これで準備完了。
制作に入ります。
(上の動画は半分の20秒で25回程度にそろえたものです。)
作る
もどる